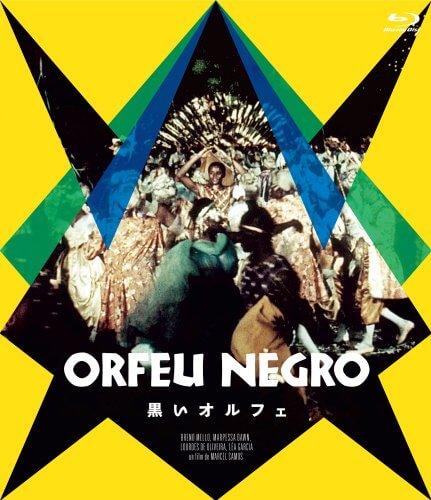ペドロ・アルモドバルの「 私が生きる肌 」をみました。
ストーリー・あらすじは以下のとおり。
天才的な形成外科医ロベルは、画期的な人工皮膚の開発に没頭していた。彼が夢見るのは、かつて非業の死を遂げた最愛の妻を救えるはずだった“完璧な肌"を創造すること。
あらゆる良心の呵責を失ったロベルは、監禁した“ある人物"を実験台にして開発中の人工皮膚を移植し、今は亡き妻そっくりの美女を創り上げていくのだった・・・。引用元:Amazon.co.jp | 私が、生きる肌 Blu-ray DVD・ブルーレイ - アントニオ・バンデラス, エレナ・アナヤ, マリサ・パレデス, ペドロ・アルモドバル
ずっと倒錯的なシーンが続くけど、超簡単に言うとアニミズムの話。ベラもロベルもやたらと模倣していたティツィアーノのヴィーナスの絵とか、ビセンテが落ち着いてから取り寄せたルイーズ・ブルジョワのカタログとかが印象的でした。あと赤と緑。あまりにも精神分析的な見方をしてください的なモチーフで溢れているので逆にしたくなくなりますけども、ロベルの家は完全に子宮ってことは言いたくなるのでいいます。
あと印象に残ったのは、虎に襲われるシーンと結婚式の庭のシーン。どちらも容赦なく性的な場面ですが。庭のシーンはノルマではなくその前の友人たちのシーンが不思議の国のアリスみたいで好き。観ながらキャタピラーとかチェシャ猫とか出てこないかなって思ってた。そんな風におとぎ話的な観かたをしたほうが、とんでもなくエロくて救いのないこの映画もポジティブに捉えられるような気がしますね。ベラがヨガに耽り、ボディスーツを解体して作った人形がまるで南太平洋の島の住人やアフリカの部族が作るようなプリミティヴなものだったのもすごく好きです。
しかしアルモドバルの映画はどれも情報量がすごく多くて観ていて疲れますね。例えばこの映画だと、ベラの監禁部屋に「 阿片は呼吸をするのを忘れるのに役立つ 」とか「 芸術は生を保証する 」とか、ストーリー的に意味あるとは思えない意味ありげな言葉や事象がたくさん出てくる。それが楽しくもあるのですが。


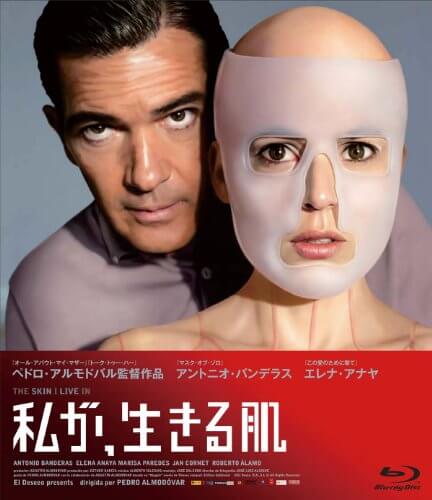

![私が、生きる肌 [DVD]](http://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51yTz2t6uEL._SL160_.jpg)