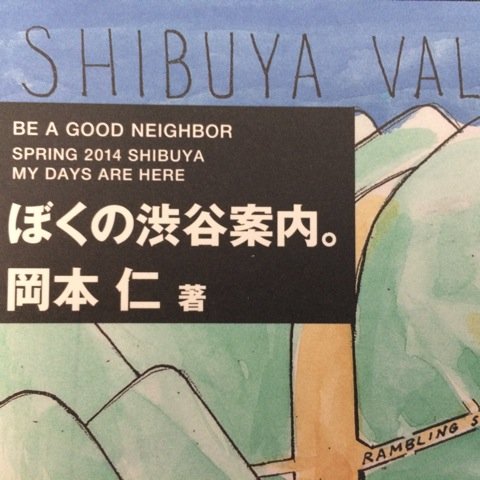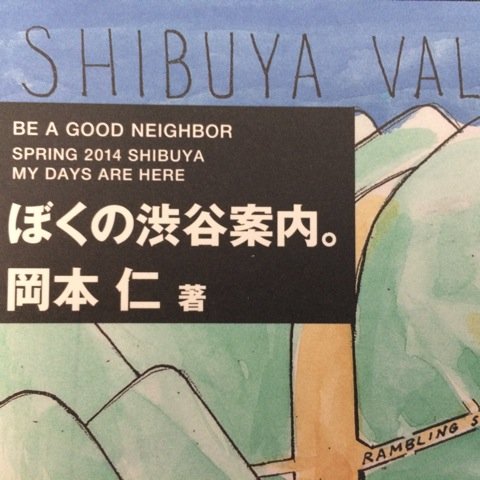
先日の岡本仁さん×小西康陽さんのトークイベントで配布された、岡本仁さんによるZINE「 ぼくの渋谷案内。 」を読みました。
トークイベントの内容については以下のリンクを参照してください。
参考URL:岡本仁×小西康陽、渋谷系を語る【SPBS『ぼくの渋谷案内。』発売記念トークイベント】
ZINEの概要。
「 ぼくの渋谷案内。 」は、SHIBUYA PUBLISHING BOOKSTOREが発刊しているZINEシリーズ「 Made in Shibuya 」の第12号。このZINEシリーズについては、SPBSのWEBサイトに以下のようなコンセプトが掲載されています。
「 Made in Shibuya 」とは、SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERSが発刊するZINEシリーズです。
街の小さな"出版する書店"でつくられる本は、その街でしかできない、その街らしいものなのに、世界中に愛読者が散らばっている。そんな風に、いちローカルとして渋谷から世界を見ていきたい。その想いから「 Made in Japan 」ではなく「 Made in Shibuya 」としてZINEを発刊していきます。引用元:SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS:SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERSのブログ
岡本さんはMade in Shibuyaの企画を担当しているらしいです。過去には長崎訓子さんや川勝正幸さんなどが渋谷にまつわるZINEをこのシリーズから発表しています。
ただこのZINEシリーズはどの号も250部限定なので、手に入れるのが非常に難しい。そんなものをブログで紹介するなんて、まるでレアなレコードを持ってるのを自慢するためだけにそのレコードをかけるDJみたいに思われるかもしれませんが、どうかご容赦いただきたいです。
肝心のZINEの内容ですが、これもまたSPBSのサイトにとても簡潔にまとめられていたので引用させていただきます。
本書は、岡本仁さんがこれまでに書いてきた、渋谷に関するコラムを中心としたヴァラエティブック。もちろん、今回のための書き下ろしも収録しています。また、岡本さんとフードライターの平野紗季子さんの2人で、渋谷の食堂やカフェをまわり、語り合ったり感想を言い合ったりの対談。さらには、『これは恋ではない』や『ぼくは散歩と雑学が好きだった。』などの著者であり、元ピチカート・ファイヴの音楽家、小西康陽さんが特別寄稿をしています。
デザインは千駄ヶ谷「 パピエラボ 」の江藤公昭さん。表紙のイラストは道玄坂「 ポスタルコ 」のマイク・エーブルソンさん。うーん、どう考えてもシブヤ・オールスターズによるスペシャルZINE。
引用元:SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERS:SHIBUYA PUBLISHING BOOKSELLERSのブログ
ヴァラエティブック、と表現されているところにもう植草甚一さんの単行本を意識してることは明らかですね。デザインも、写真の使い方といいテキストの段組みといい、その意識を存分に感じることができます。
ほかにも少し補足すると、岡本さんによる過去のコラムは、ブルータスに変名で掲載された文章やリラックスのフリーペーパーでの川勝氏との対談のほか、彼のブログにアップされたもので主に構成されているので、アーカイブを遡れば読めないこともないです。
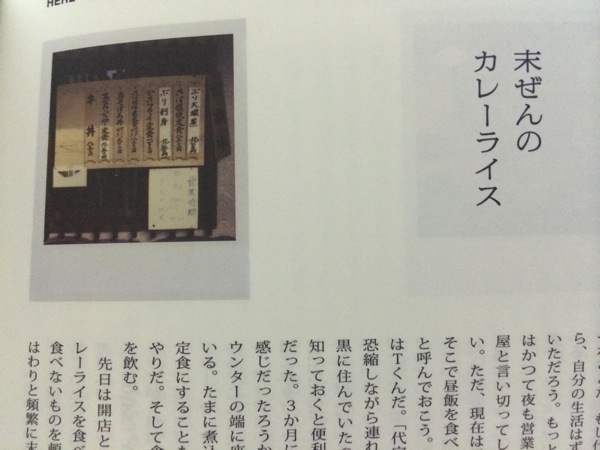
しかし、やはり印象深かったのは本誌のエクスクルーシヴのひとつである平野紗季子さんと渋谷を散策しながらの対談でした。東京に永く住む食狂いの( 、と表現しても差し支えないほどにあらゆるグルメスポットに造詣の深い )二人による、ディープで粋な渋谷案内。
岡本さんは会話のなかで、平野紗季子さんとの対談、というより渋谷のお店にご飯を食べに行くことを一番最初に企画した、と話しています。その理由として「 世代の違いによる味覚の違いを話したかった 」と続けるのですが、この発言の中には、岡本さんが彼自身と平野紗季子さんとは食に関して近い感覚を持っていると判断した、という含意を感じるのです。それは単純な食べ物の好みということではなく( むしろ二人の食べ物の好き嫌いは対談中はことごとく合わない )、気に入るお店の種類や食に対する姿勢、といった部分で近いということ。だからこそ年齢の違いによる味覚の違いに焦点を絞れると考えたのではないか、などとこの対談の企画意図を推測することができます。
だけど二人は対談中食べた料理の味に関する話をほとんどしません。したとしても単純においしいとだけ言ったり、あるいは出されたものではなくほかの店の食べ物の話だったりする。
僕は雑誌というものは情報を与えるというより読者の意識を喚起するものであるべき、という風に考えているのですが、二人が食の話をしているにも拘らず料理の味に対する意見があまり出てこないというのも、結局のところまさしくその意識喚起を目的にしているような気がしてならないのです。それは、この対談で岡本さんが次のような言葉をみれば明らかだと思います。
「 食べ物を書くことは難しい。味の区別を言葉にできない。どのような味がしたから美味しいのではなくて、美味しいは口に入れる瞬間に美味しいので...。だから『美味しい』という言葉をどのくらいのタイミングで文章に入れるかを考えて書くようにしている。だから、ちゃんと読まれると『美味しい』としか書いてないから困る...( 笑 )でも、その文章を読んで、食べてみたい、と行動に繋がるような表現ができればいいと思っている。それしかできない... 」
最後に。
そんな雑誌的情報の至高点のような対談ですが、食の部分以外でも非常に興味深い、岡本さんの生き方や考え方が滲み出ているような発言がたくさん出てきて非常にエキサイティングでした。
あとすごく個人的なことですが、この対談を読んで、今まで「 若い 」「 美人 」「 成功者 」という本当にバカみたいな理由であまりいい印象を持っていなかった平野紗季子さんがすごく好きになりました。食の女大瀧詠一、というジェンダー&偏見極まりないキャッチフレーズをつけてあげたいほどに。
もちろん平野紗季子さんの話には、抗いようのない、若さから来る独善的思考を感じる場面も多々あるのですが眼をつむれる程度で、好印象のほうが先に立つくらい魅力が引き出されています。少なくとも岡本さんと対等に渡りあっているように見えますし、そのおかげで、二人は持っている精神や嗜好は一緒で、今まで通ってきたルートやみてきたもの、スタートする時期が違うだけのような気がする、なんてことを思えてしまうのです。
その辺も含めて本当にこのZINEを読めてよかった、なんて、やっぱり少し自慢っぽくなってしまいごめんなさい...
おまけ。
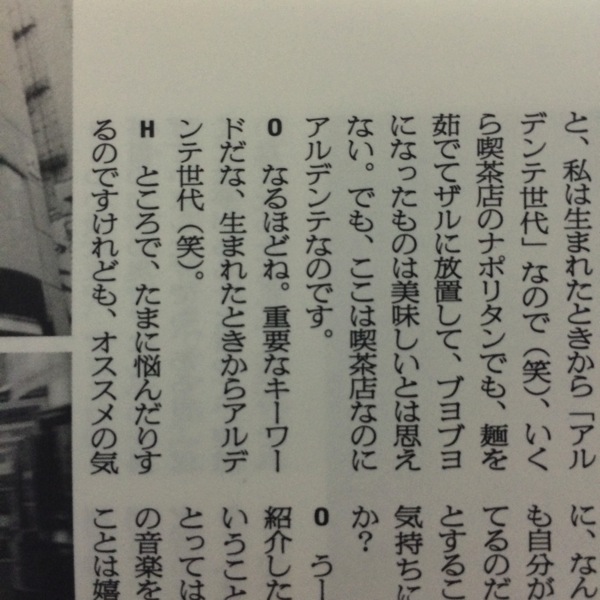
対談のなかで平野紗季子さんの文末が「 〜なのです 」で終わることが多かったのですが、これは原稿チェックで修正されたのか。それとも本当にこういう話し方をする人なのか。気になってますます彼女に興味を持ってしまいました。
関連リンク
ランドスケーププロダクツ
売り上げランキング: 132,883